西部邁『思想の英雄たち――保守の源流をたずねて』
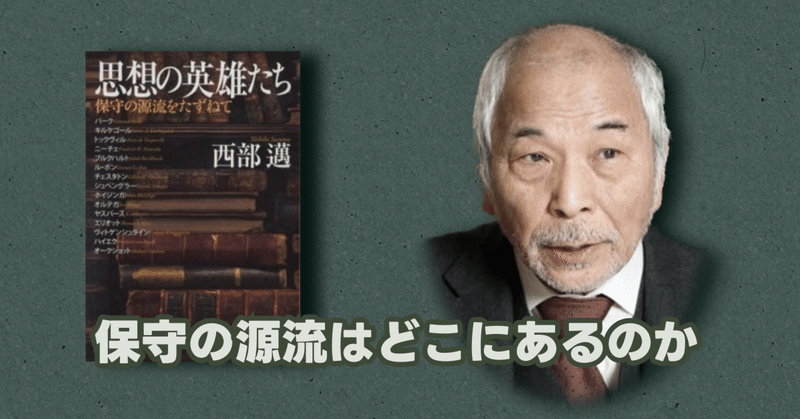
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回は西部邁著『思想の英雄たち』について議論していきたいと思います。
『思想の英雄たち』
1996年の西部邁氏の『思想の英雄たち』は、雑誌『発言者』とその後続雑誌『表現者』という雑誌に寄稿していた日本の保守派の西部グループの骨格を成すような著作だったと思います。
初期の『ソシオ・エコノミックス』や『経済倫理学序説』のような経済学に関する著作から多く舵を切って、1990年代後半から、『思想の英雄たち』(1996)、『知性の構造』(1996)、『知識人の生態』(1996)、『虚無の構造』(1999)、『エコノミストの犯罪』(2002)などを残しています。
2005年の自伝的小説『友情 ある半チョッパリとの四十五年』は高校時代の西部氏と同級生だった在日朝鮮人との友情の話で、当時、日本の保守派の間で起こっていた在日朝鮮人、韓国・北朝鮮批判に、やんわりと一石を投じるかのような面がありました。
今回取り上げたいのは現在は入手困難となっている『思想の英雄たち』で西部氏が紹介している、保守の源流と目される思想家の著作について触れていきたいと思います。
エドマンド・バーク
エドマンド・バークは欧米では保守論には欠かすことができない人物の一人として様々な著作で言及されています。
日本で翻訳されたものでいいますと、アンソニー・クイントンの『不完全性の政治学』やラッセル・カークの『保守主義の精神』などでもバークは中心主題となっています。
初期の美学に関する著作『崇高と美の観念の起原』は哲学者のイマヌエル・カントにも影響を与えています。バークは崇高と美が異なるものであるとし、崇高であるものを美という概念から切り離します。
バークの初期の抽象論的議論はその後の『フランス革命の省察』といった具体的なフランス革命などの事件を題材とした論議に、緻密な修辞的な技巧を散りばめながら批判的にそれを論じるのに役立てられています。
バークはフランスのジャコバン主義者の形而上学的抽象論を痛烈に批判していますが、一方で巧みに抽象論を織り交ぜながらそれを批判するというアクロバティックな文体で表現しています。
日本ではフリーメイソンやイルミナティの議論をすると陰謀論として主流派の保守が批判的に論じるわけですが、歴史的に見れば、『フランス革命の省察』や『バーク政治経済論集』を読むと、初期の保守思想がイルミナティ・フリーメイソン批判と関係があるということが分かります。
大衆批判の原点
『思想の英雄たち』の中で特に大衆批判としての側面から読み解くことができるのは、ゼーレン・キルケゴール、ギュスターヴ・ル・ボン、ホセ・オルテガ・イ・ガセットです。
キルケゴールの『現代の批判』を大衆批判の出発点の一人として、社会心理学者のル・ボンの『群衆心理』、ドイツで生物学者ユクスキュルの環世界論を学びパースペクティヴィズムを導入した哲学者のオルテガの『大衆の反逆』などを紹介しています。
ル・ボンは国内ではあまり邦訳がありませんが、オルテガの著作は日本では古くから翻訳されており、国立国会図書館デジタルコレクションでも読めるものもあります。『ドン・キホーテに関する思索』の次の言葉が有名です。
私は、私と私の環境である。そしてもしこの環境を救わないなら、私をも救えない。
ヨーロッパでは科学の発達もあり、オルテガの時代には、ドイツ観念論にみられるような思弁的な議論から、その哲学的考察にもより科学的な議論が持ち込まれるようになっています。
ニーチェとチェスタトン
『思想の英雄たち』のなかではニーチェとチェスタトンが対比的に論じられています。「神は死んだ」と宣言し、ニヒリズムやルサンチマン、超人論、永劫回帰、力への意志など、非常に衝撃的な内容の著作を多くの残したニーチェを保守思想家とみるのはやや無理があるとは思いますが、『不完全性の政治学』の保守の三つの立場、伝統主義・懐疑主義・有機体主義という点でいいますと、深い洞察で西洋文明を批判したニーチェの精神性と保守思想に親和性がないかといえば、必ずしもそうとはいえないような部分はあるかもしれません。
見方を変えますと、西部邁氏はニーチェに見られるような深い洞察と毒々しいまでの批判的視点で世界をのぞき込むことを保守派に求めたと見ることもできると思います。
残念ながら日本の主流の保守派にそれを求めるのはおそらく難しいでしょう。
一方、パラドキシカルなレトリックを駆使したイギリスの小説家ギルバート・チェスタトンはニーチェを批判し、カトリックを全面的に支持し、『正統』論を展開しました。
西部邁はチェスタトンの諧謔(ユーモア)に焦点を当て、そのパラドキシカルな正統論の重要性を指摘します。
チェスタトンの面白さは民主主義批判を「おとぎの国の倫理学」という章で論じるところなどにも見られます。
私の最初にして最後の哲学、私が一点の曇りもなく信じて疑わぬ哲学――私はそれを子供部屋で学んだ。
私個人の意見を言いますと、私にはチェスタトンに見られるようなキリスト教に対する深い信心はありませんが、それでも、彼のパラドキシカルな正統論には魅力があることを認めざるをえません。
西部邁が議論にユーモアを織り込むことに重点を置いていたのは、現在も彼の著作を読んだり、動画をみたりすると感じられますが、けっしてチェスタトン譲りというわけでもなかったのでしょうけれど、それでも彼の逆説的で、天地がひっくりかえるかのような独特のレトリックから一定の影響を受けていたというのは推測するに難しくはないでしょう。
チェスタトンの親友の一人ヒレア・ベロックは『ユダヤ人』の中でユダヤ人がロシア革命を起こしたということを指摘しています。チェスタトンもこの種の事実は掴んでいたと思います。この辺りは日本の保守派は今後丹念に調べていく必要があると思います。
保守と歴史
歴史学的視点では、オズワルド・シュペングラー、ヤーコプ・ブルクハルト、ヨハン・ホイジンガが紹介されています。
ブルクハルトの『世界史的考察』はヘーゲル批判としての側面があります。ブルクハルトは自然と歴史の関係性について次のようなことも言っています。
最後に、自然科学と数学にたいするわれわれの関係について、この場所でさらに一言述べておくのが当を得ていると思う。この二つの学問は利害関係を離れて唯一のわれわれの仲間であるが、一方、神学と法学はわれわれを押さえつけようとし、そうでないまでも攻撃の材料として利用しようとする、また哲学はあらゆるものの上に立とうとしているが、実はあらゆるもののもとに身をよせて生きながらえているのである。
自然においては、滅亡は外的原因によってしか起こらない。すなわち、地殻の大変動、気候の大変動のために、より弱い種がより厚かましい種によって圧倒されたり、より高貴な種がより劣悪な種によって圧迫されたりするのがそれである。歴史においては、滅亡はつねに内的衰退、生命の消尽によって準備される。この段階にいたって初めて、外的動因がすべてに終止符を打つのである。
ホイジンガは遊ぶものとしての人「ホモ・ルーデンス」という概念を提唱したことで知られていますが、『明日の蔭の中で』において現代社会の病理を描写しています。
私たちは憑かれた世界に生きている。そして私たちはそれを知っている。ある日突然妄想が起こって、狂気の沙汰となり、このあわれなヨーロッパ人を転倒させ、愚鈍かつ錯乱の状態に陥らせたとしても、意外に思う人はいないだろう。—―まだエンジンはぶんぶん鳴り、旗はたなびいているが、精神はうつろになっている。
こういった言葉で始まるこの著作は中世の神学者ベルナール・ド・クレルヴォ―の次のような引用文から始まります。
この世には夜がある。しかも、少なからざる夜が。
私たちの生きている世界は闇が存在し、その闇は私たちが思っているよりもはるかに大きいものである、というのは、クレルヴォーが生きていた中世の頃、そして、おそらくはそれよりもずっと前から感じ取られていたことであり、ホイジンガがこの著作を書いた第二次世界大戦がはじまる少し前、そしてそればかりでなく、2022年のこの世界でも感じられることでしょう。
この著作の中でフリーメイソン陰謀論について否定的に論じられていますが、第二次世界大戦を経験したこの時代の住人は、陰謀論特有の幻像に振り回されることなく、判断の邪悪に陥らないように、注意深くこの問題を見ていく必要があるかもしれません。
いずれにせよ、現代の病理、その一つは文化的小児病(ピュエリリズム)と表現されていますが、この種の病理性と向き合いながら、現代社会を生きていく必要があるものと思います。
個性の滅却
詩人のトーマス・S・エリオットは、『伝統と個人の才能』の中で、次のようにいいます。
詩は情緒の解放ではなくて情緒からの逃避であり、個性の表現ではなくて個性からの解放である。
エリオットは、詩において情を表現するためには、自分の情、そしてあらゆる人々の情を凝視し、俯瞰しなければならず、詩的才能とはプライベートから離れて、よりパブリックなものとならなければならないと考えます。
そのためにはレトリックを理解しなければならず、伝統に寄り添う必要があります。恐らく何も学ばなくても直観的にそういったものを表現できる人もいるとしても、結局な何らかの意味でかつて誰かが歩んだ道に近い道を、そしてその道の先を歩んでいることになるのではないかという意味でも、伝統とは切り離せないと見ることもできるのでしょう。
この点は小林秀雄などもエリオットの議論を用いながら、ゴッホを論じています。
エリオットの『荒地』や『四つの四重奏曲』など、現代的な表現でありながら、多くの伝統的な技巧や知識を駆使しています。エリオットは詩人論を多く書いていますが、実際にテニスンやボードレールといった有名な詩人に見られるような表現が多く盛り込まれています。
個人的にはエリオットの『聖灰水曜日』やカンタベリー大司教トマス・ベケット暗殺事件を題材とした詩劇『寺院の殺人』などが好きです。
他にもフリードリヒ・ハイエクやルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン、マイケル・オークショットなど重要な学者や哲学者についても論じられていますが、今回はとりあえずここまでとします。
関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。
今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。